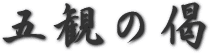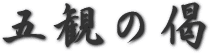ご か ん げ
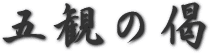
道元禅師は『赴粥飯法』一巻を著して、食事の作法を大変ていねいに示していらっしゃいます。その冒頭で、「本当に仏の教えが自分の身に備わったならば、仏としての食事の作法がきちんと行われるはずである。仏としての食事作法が正しく行ぜられるならば、自ずと仏の教えが自分の身に備わる」つまり、「法等食等(ほうとうじきとう)」という考え方を強調しています。
【五観の偈】とは
食物が一同に行き渡って槌または戒尺が鳴ると、合掌低頭して一緒に唱える偈文(げもん)のことをいいます。
|
一(ひとつ)には功の多少を計り、彼の来処(らいしょ)を量(はか)る。
(食物が供されるまでの人々の苦労及び施主の恩に感謝し頂くこと)
二(ふたつ)には己(おのれ)が徳行(とくぎょう)の、全欠(ぜんけつ)を忖って(はかって)供(く)に応ず。
(自己の行いを見つめて食物を頂くのに値するか推し量ること)
三(みつ)には心を防ぎ過(とが)を離(はな)るることは、貧等(とんとう)を宗(しゅう)とす。
(多く貧らないように慎むこと)
四(よつ)には正(まさ)に良薬を事とするは、形枯(ぎょうこ)を療(りょう)ぜんが為なり。
(健全なる心身を維持する為に必要な薬として頂くこと)
五(いつ)には成道(じょうどう)の為の故(ゆえ)に、今此(いまこ)の食(じき)を受(う)く。
(道を修める為に此の食を頂くこと)
|
|